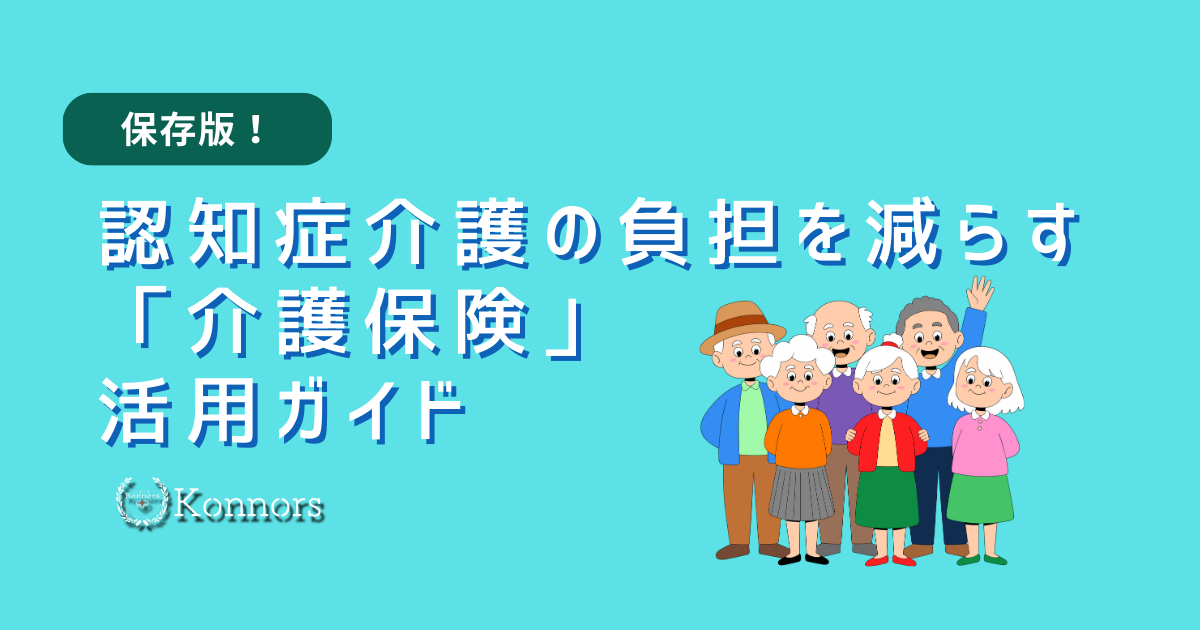はじめに:介護の不安を専門家と一緒に解消しましょう
「認知症と診断されたけれど、手順がわからない」
「介護負担が限界」
そんな悩みを抱えるあなたへ。
認知症リハビリテーション専門士・ケアマネジャーとして20年以上現場に立つ私が、介護保険制度の活用法を徹底解説します。
この記事は、単なる制度説明ではなく、現場のプロしか知らない「認定調査の攻略法」や「サービス拒否への対策」まで踏み込んだ実践ガイドです。
1. 介護保険制度とは?仕組みとメリット

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える公的制度です。
- 対象: 40歳以上(第2号被保険者)、65歳以上(第1号被保険者)
- 費用負担: 原則1割(所得により2~3割)でサービス利用が可能。
- 最大のメリット: プロ(ケアマネジャー)が仲介に入り、数千円〜という安価な費用で専門的なケアや福祉用具を利用できること。
2. 申請からサービス利用までの5ステップ【最短ルート】
介護サービスを使うには「要介護認定」が必須です。以下の流れで進めます。
| ステップ | アクション | 内容 |
| STEP 1 | 申請 | 市区町村の窓口、または「地域包括支援センター」へ申請書を提出。 |
| STEP 2 | 認定調査 | 調査員が自宅を訪問し、心身の状態を確認(重要局面)。 |
| STEP 3 | 審査・判定 | コンピュータ判定と主治医意見書をもとに審査会がレベルを判定。 |
| STEP 4 | 結果通知 | 申請から約1~2ヶ月後に認定結果(要支援1〜要介護5)が届く。 |
| STEP 5 | ケアプラン作成 | ケアマネジャーを選定し、計画を作成してサービス開始。 |
【プロのアドバイス】
申請から結果が出るまでの期間も、「暫定ケアプラン」を作成すればサービス利用は可能です。
ただし、想定より低い介護度が出た場合、差額が自己負担になるリスクがあります。必ずケアマネジャーと相談しながら進めてください。
3. 【目的別】利用できる主な介護サービス一覧
自宅で過ごすか、施設に入るか。
目的別に代表的なサービスを比較しました。
① 居宅サービスの一例(自宅で生活を続けたい方)
| サービス名 | 内容・特徴 | おすすめのケース |
| 訪問介護 | ヘルパーによる身体介護・生活援助 | 買い物、掃除、入浴介助が必要な方 |
| 訪問看護 | 看護師による医療処置・健康管理 | インスリン注射や床ずれ処置が必要な方 |
| 訪問リハビリ | 専門職(PT/OT/ST)による自宅リハビリ | 通所困難だが身体機能を維持したい方 |
| 通所介護 (デイサービス) | 施設での入浴・食事・レクリエーション | 家族の休息(レスパイト)、日中の見守り |
| 福祉用具貸与 | 車椅子、電動ベッド等のレンタル | 転倒予防、自立支援環境を整えたい方 |
② 地域密着型・施設サービスの一例(専門的なケアが必要な方)
- 小規模多機能型居宅介護: 「通い・泊まり・訪問」を同じスタッフが柔軟に対応。環境変化に弱い認知症の方に最適。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム): 認知症の診断を受けた方専用の、少人数(5〜9人)での共同生活。家事分担など「生活リハビリ」を実施。
- 特別養護老人ホーム(特養): 要介護3以上。「終の棲家」として人気が高い公的施設。
4. 費用目安:1ヶ月に使える金額の壁
介護度に応じて利用限度額(区分支給限度基準額)が決まっています。これを超えた分は全額自己負担となります。
【1割負担時の利用限度額目安(月額)】
- 要支援1: 約5,032円(利用枠:約5万円)
- 要介護1: 約16,765円(利用枠:約16万円)
- 要介護3: 約27,048円(利用枠:約27万円)
- 要介護5: 約36,217円(利用枠:約36万円)※地域やサービス加算により変動します。
5. 【実録事例】サービス拒否・よそ行き対応をどう攻略するか?
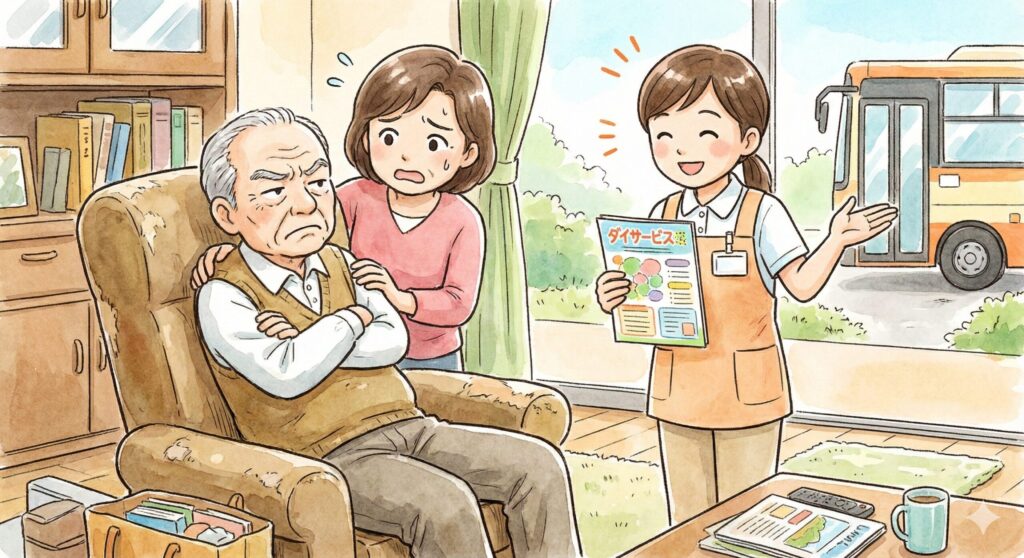
事例:Aさん(78歳男性・アルツハイマー型認知症)
「俺はボケてない!世話なんて必要ない!」と頑固なAさんが、デイサービスに通うまでの実話ドキュメントです。
課題:認定調査での「よそ行き顔」
普段は入浴拒否や物盗られ妄想があるのに、調査員の前では「毎日風呂に入っています(嘘)」とシャンと答えてしまう現象。
✅ 解決策:メモ渡し作戦
家族が事前に「普段の困りごとメモ」を作成。Aさんが席を外した隙に調査員へ手渡しました。「実際は2週間入浴していない」という事実と「主治医意見書」が合致します。
結果 → 「要介護1」と正しく認定されました。
課題:プライドによる「サービス拒否」
「年寄りの集まる場所なんて行きたくない」とデイサービスを拒絶。
✅ 解決策:目的のすり替え(リフレーミング)
ケアマネジャー(私)は「介護」という言葉を封印しました。
「足腰が弱るとゴルフができなくなります。
スポーツジムのような場所でトレーニング(リハビリ)をしませんか?」と提案。
結果 → 「リハビリなら行く」と納得し、今では週1回通所されています。
6. 認知症介護のよくある質問(FAQ)
Q1. 家族が認知症かも?まずどこに相談すればいいですか?
A. 「地域包括支援センター」一択です。
高齢者のよろず相談所です。無料で相談でき、本人不在でも家族だけで相談可能です。
Q2. 認知症の本人がデイサービスを嫌がります。どうすれば?
A. 正論での説得は避け、「体験」から始めましょう。
「お風呂に入ろう」ではなく「美味しいお茶を飲みに行こう」と誘う、あるいは医師やケアマネジャーといった「第三者」から勧めてもらうのが効果的です。
Q3. ケアマネジャーは変更できますか?
A. はい、可能です。
相性は介護の質に直結します。合わないと感じたら、地域包括支援センターや事業所管理者に相談してください。
まとめ:あなたらしい介護を実現するために
介護保険は「申請」がゴールではなく、「本人が納得して利用すること」がスタートラインです。
専門知識を持つケアマネジャーを味方につけ、使える資源は全て使い倒してください。
一人で抱え込まず、まずは地域包括支援センターへの電話一本から始めましょう。
■ 執筆:菅原 浩平 (コナーズ代表 / 介護支援専門員 / 介護福祉士)
現場経験20年以上。ケアマネジャーとして多くのプラン作成に携わる一方、家族の視点と経営者の視点を持ち合わせ、現在は「家族の笑顔を守る」ためのメディア運営を行う。
■ 監修:菅原 嘉奈 (認知症リハビリテーション専門士 / 介護支援専門員 / 介護福祉士)
介護現場での実務経験に加え、専門的なリハビリ知識を活かした「自宅でできる認知症改善」を指導。科学的根拠に基づいたアプローチで、ご本人だけでなくご家族の負担軽減を目指す。コナーズ共同代表。
【無料プレゼント】認知症の症状改善メソッドを公開中!
介護サービスで生活を支えることは大切ですが、「認知症の症状そのもの」が落ち着けば、介護はもっと楽になります。
「暴言が減った」「笑顔が増えた」と話題の、自宅でできる『認知症改善の教科書』を、現在公式LINE登録者限定で無料プレゼントしています。
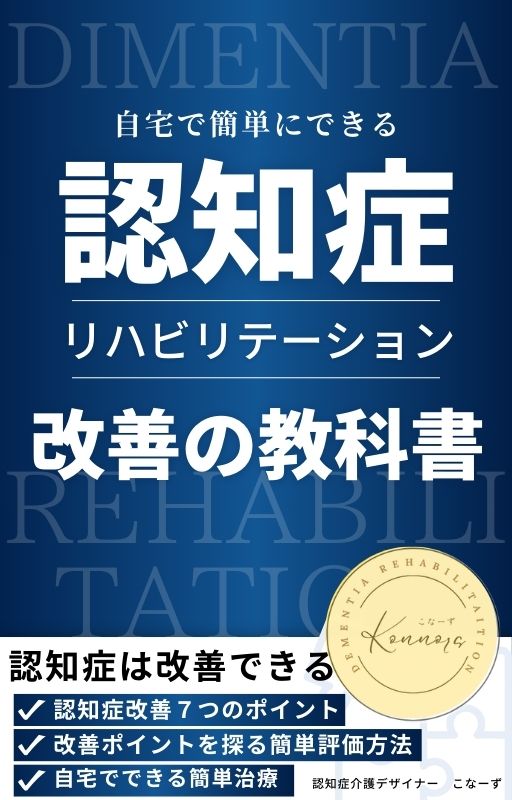
▼今すぐ下のリンクをクリックして特典を受け取る▼