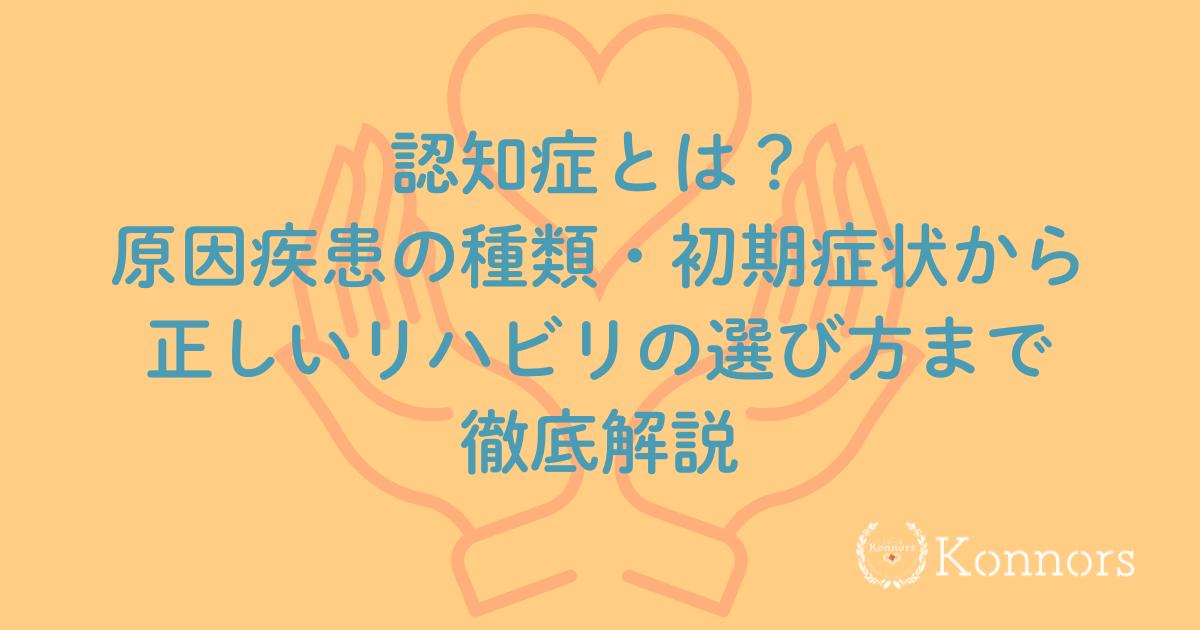はじめに:認知症と原因疾患の関係性
「最近、親の物忘れがひどくなった」
「性格が変わった気がする」
そのような変化を感じたとき、それが「加齢」によるものなのか、それとも「認知症」のサインなのか、不安を感じる方は少なくありません。
認知症は早期発見と正しい原因の特定、そして「適切な評価に基づくリハビリ」を行うことで、進行を遅らせたり、生活の質(QOL)を維持・改善したりすることが可能です。
本記事では、認知症の定義や主要な原因疾患(アルツハイマー型など)、見逃してはいけない初期症状のチェックリスト、そして本当に効果的なリハビリテーションのあり方について解説します。
1. 認知症とは「病名」ではなく「状態」のこと
まず理解しておきたいのは、認知症とは単一の「病気」の名前ではなく、脳の機能低下によって日常生活に支障をきたしている「状態(症候群)」を指すということです。
何らかの病気が原因(原因疾患)となり、脳の神経細胞が破壊されたり減少したりすることで、記憶、思考、判断、言語、視空間認識などの認知機能が低下します。
「原因疾患」の特定が重要な理由
認知症を引き起こす原因疾患は70種類以上あると言われています。
「認知症」とひとくくりにされがちですが、どの病気が原因かによって、現れる症状、進行スピード、治療法、そして適切な対応が全く異なります。
そのため、「認知症かもしれない」と思った段階で専門医による診断を受け、原因疾患を突き止めることが、その後の生活を守るための第一歩となります。
2. 【一覧表】認知症の4大原因疾患と特徴
認知症の原因疾患は大きく「神経変性疾患」「脳血管性認知症」「その他の疾患」に分類されます。
ここでは代表的な4つの原因疾患について解説します。
| 分類 | 疾患名 | 特徴と主な症状 |
| 神経変性疾患 | アルツハイマー型認知症 | 【最も多いタイプ】 脳内にアミロイドβなどが蓄積し、神経細胞が死滅。 ・特徴: 物忘れ(記憶障害)から始まり、徐々に進行する。 ・症状: 時間や場所がわからなくなる、迷子になるなど。 |
| 神経変性疾患 | レビー小体型認知症 | 【幻視や身体症状が特徴】 レビー小体というタンパク質が蓄積。 ・特徴: 調子の良い時と悪い時の波がある。 ・症状: 幻視(いないはずの人が見える)、手足の震え・筋肉のこわばり(パーキンソン症状)。 |
| 神経変性疾患 | 前頭側頭型認知症 | 【性格・行動の変化】 前頭葉や側頭葉が萎縮する。 ・特徴: 記憶障害よりも性格変化が目立つ。 ・症状: 万引きなどの社会的ルールの無視、同じ行動を繰り返す(常同行動)、感情の抑制がきかない。 |
| 脳血管障害 | 脳血管性認知症 | 【脳梗塞などが原因】 脳梗塞や脳出血による脳の損傷。 ・特徴: 損傷部位により症状が異なる(まだら認知症)。 ・症状: 意欲の低下、歩行障害、感情失禁など。脳卒中の発作ごとに段階的に悪化しやすい。 |
その他の原因(治療可能な認知症)
以下のような疾患は、手術や治療によって症状が劇的に改善する可能性があります(治る認知症と呼ばれることもあります)。
- 正常圧水頭症: 脳室に髄液が溜まり圧迫される。歩行障害や尿失禁が出る。
- 慢性硬膜下血腫: 頭を打った後などに血が溜まる。
- 内科的疾患: 甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏症など。
3. 「まさか認知症?」早期発見のためのセルフチェックリスト
「年のせい」で見過ごされがちな変化も、認知症のサインかもしれません。
ご家族の様子が以下に当てはまらないか確認してみてください。
① 記憶・判断力の低下(中核症状)
- [ ] 新しいことが覚えられない: 同じことを何度も言ったり、聞いたりする。
- [ ] 置き忘れ: 財布や通帳など、貴重品をどこに置いたか思い出せない。
- [ ] 金銭管理の失敗: 小銭での支払いができない、ATMの操作がわからなくなった。
- [ ] 手順の混乱: 料理の味付けが変わった、段取りが悪くなった。
- [ ] 季節感の喪失: 真夏に冬服を着るなど、季節や状況に合った服が選べない。
② 言語・空間認識の低下
- [ ] 言葉が出ない: 「あれ」「それ」が増えた。物の名前が出てこない。
- [ ] 道に迷う: 慣れ親しんだ道で迷う、いつも通る場所がわからなくなる。
- [ ] 動作の拙劣: ボタンの掛け違い、着替えに時間がかかる、食べこぼしが増えた。
③ 性格・心理面の変化(BPSD:行動・心理症状)
- [ ] 意欲低下: 趣味や好きだったことに無関心になった。入浴や整容を嫌がる。
- [ ] 易怒性: 以前より怒りっぽくなった、性格が攻撃的になった。
- [ ] 妄想: 「財布を盗まれた」「配偶者が浮気している」など事実無根のことを言う。
- [ ] 幻覚: 「部屋に知らない子供がいる」など、ないものが見えている(特にレビー小体型に多い)。
これらの症状が見られた場合、MCI(軽度認知障害)の段階である可能性もあります。
この段階で適切な介入を行えば、本格的な認知症への移行を遅らせたり、防いだりできる可能性があります。
4. 認知症の診断プロセス
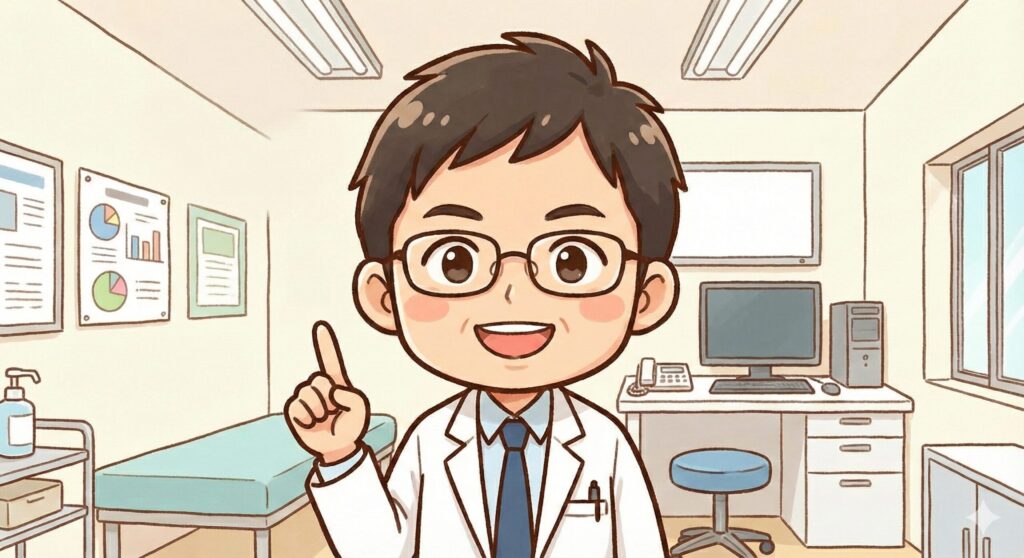
医療機関では、以下の流れで確定診断を行います。複数の検査を組み合わせ、慎重に判断します。
- 問診: 本人および家族から、生活状況や変化についてヒアリング。
- 神経学的検査・身体診察: 記憶力テスト(長谷川式など)、反射、麻痺の有無などを確認。
- 画像検査:
- CT/MRI: 脳の萎縮、脳梗塞、腫瘍、水頭症などを確認。
- 脳血流シンチグラフィ: 脳の血流低下部位を調べ、アルツハイマー型やレビー小体型の鑑別に役立てる。
- 血液検査: ビタミン欠乏や甲状腺機能など、内科的原因を除外するために実施。
5. 本当に効果のある「認知症リハビリテーション」とは?
認知症と診断された後、重要になるのがリハビリテーションです。
目的は「完治」ではなく、認知機能の低下を遅らせ、残された能力を最大限に活かし、自分らしく生活できる期間を延ばすことです。
しかし、多くの現場で行われているリハビリには大きな課題があります。
多くのリハビリ現場が抱える「評価不足」の問題
一般的なリハビリ(例:脳梗塞後の歩行訓練)では、以下のPDCAサイクルが回されます。
- 評価: 身体機能を測定し、課題を明確にする。
- 計画: 個別にプログラムを作成する。
- トレーニング: 実施する。
- 再評価: 効果を測定し、プログラムを修正する。
しかし、認知症のリハビリ現場では、「1. 評価」と「4. 再評価」が抜け落ちているケースが非常に多いのが現状です。
「とりあえず塗り絵」の危険性
個別の評価を行わず、「認知症だからとりあえず塗り絵や計算ドリルをやっておきましょう」というアプローチは、医学的根拠に基づいたリハビリとは言えません。
例:原因が「脱水」にある場合
認知機能低下の原因が「水分不足(脱水)」にある場合、必要なのは計算ドリルではなく「適切な水分補給」です。
原因(評価)を見誤ったまま的外れなトレーニングを行っても効果は出ませんし、その間に脱水が進み、生命に関わるリスクさえあります。
正しいリハビリとは、一人ひとりの「脳の状態」「生活背景」「身体状況」を専門的に評価し、その人に今必要なプログラムを提供することです。
6. まとめとご提案
認知症は、原因疾患によって症状も対処法も異なります。
「年のせい」と自己判断せず、早期に医療機関を受診することが、ご本人とご家族の未来を守ります。
そして、診断後の生活を支えるためには、**「形だけのリハビリ」ではなく、「適切な評価に基づいた個別リハビリ」**が不可欠です。
【コナーズ】の個別リハビリテーション
私たち【コナーズ】では、画一的なレクリエーションではなく、患者様一人ひとりの状態を専門的に評価し、**「根拠のある個別リハビリテーション」**をご自宅で提供しています。
- 病院のリハビリが終わってしまった
- デイサービスの効果に疑問を感じている
- 親の状態に合った、正しい接し方やケア方法を知りたい
このようにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
専門家が現状を分析し、ご家庭でできる最善の解決策をご提案いたします。
認知症に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 認知症は必ず進行しますか?
A1. アルツハイマー型などは進行性ですが、薬やリハビリ、生活環境の調整によって進行を緩やかにすることは可能です。また、正常圧水頭症など原因によっては治療により改善するものもあります。
Q2. 物忘れと認知症の違いは?
A2. 加齢による物忘れは「体験の一部を忘れる(夕食のメニューを忘れる)」のに対し、認知症は「体験そのものを忘れる(夕食を食べたこと自体を忘れる)」のが特徴です。また、認知症は自覚がない場合が多いです。
Q3. 家族が受診を拒否します。どうすればいいですか?
A3. 「健康診断に行こう」「最近疲れやすいから一緒に診てもらおう」など、認知症という言葉を使わずに受診を促すのが一つの方法です。まずは地域包括支援センターやかかりつけ医に事前に相談することをお勧めします。
無料相談のお申し込みは、コナーズ公式LINEから承っております。
コナーズ公式LINE登録はこちら

【参考資料】
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
- 国立長寿医療研究センター:https://www.ncgg.go.jp/
- Alzheimer’s Association:https://www.alz.org/