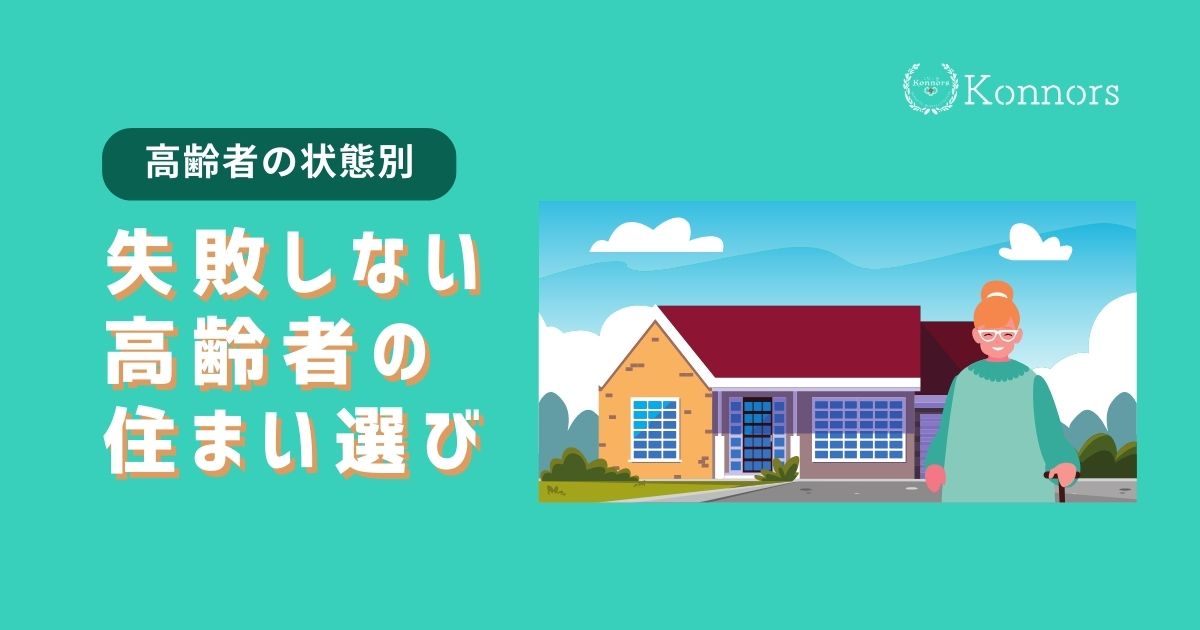はじめに
人生100年時代と言われる現代において、高齢期の住まいは、その後の生活の質を大きく左右する重要な要素です。
しかし、インターネットで検索しても多くの情報が溢れており、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も少なくありません。
この記事では、高齢者の方とそのご家族が、それぞれの状態や希望に合った住まいを選び、安心して暮らすためのポイントを分かりやすく解説します。
ぜひ、最後までお読みいただき、住まい選びの一助としてください。
高齢者の状態別 住まいの種類と特徴

高齢者の住まいの種類は多岐にわたり、ご本人の身体状況や介護の必要性によって最適な選択肢は異なります。ここでは、高齢者の状態別に、代表的な住まいの種類とその特徴を詳しく見ていきましょう。
元気な高齢者向け:アクティブシニアが快適に暮らす住まい
まだまだ活動的に生活を楽しみたい高齢者の方には、自由度が高く、生活支援サービスが充実した住まいがおすすめです。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー構造で、安否確認や生活相談などのサービスが付いた賃貸住宅です。食事の提供や介護サービス(外部の事業者と契約が必要な場合が多いです)を受けられるところもあり、自立した生活を送りながらも、将来への安心を備えたい方に向いています。比較的自由度が高く、ご自身のペースで生活できるのが魅力です。
- ポイント: バリアフリー構造、安否確認、生活相談サービスが基本です。食事や介護サービスは施設によって異なります。将来的に介護が必要になった場合、外部サービスを利用しながら住み続けられる可能性があります。
- こんな方におすすめ: 自立した生活を送りたいが、将来に備えて安心できる環境に住みたい方。ご夫婦で入居を希望する方。
シニア向け分譲マンション
シニア向け分譲マンションは、高齢者が快適に暮らせるようバリアフリー設計が施され、共用施設や生活支援サービスなどが充実しているマンションです。所有権があるため、資産として残せる点が特徴です。他の入居者との交流も期待でき、活動的なシニアライフを送りたい方にとって魅力的な選択肢となります。
- ポイント: バリアフリー設計、共用施設(レストラン、フィットネスジムなど)、生活支援サービスが充実しています。所有権があるため、資産となります。
- こんな方におすすめ: 健康で活動的なシニアライフを送りたい方。ご自身の住まいを持ちたい方。
- 注意点: 一般的なマンションに比べて初期費用が高額になる場合があります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、掃除などの生活支援サービスが中心の施設です。介護サービスが必要になった場合は、外部の居宅介護サービスなどを利用することになります。比較的元気な高齢者で、身の回りのことは自分でできるけれど、家事負担を減らしたいという方に向いています。
- ポイント: 食事、洗濯、掃除などの生活支援サービスが提供されます。介護サービスは外部利用が基本です。
- こんな方におすすめ: 身の回りのことは自分でできるが、家事の負担を減らしたい方。他の入居者との交流を希望する方。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
ケアハウスは、比較的低料金で利用できる高齢者向けの施設です。
食事の提供や生活相談、緊急時の対応などのサービスがあり、自立した生活を送れるものの、多少の不安がある方に向いています。
介護が必要になった場合は、外部の介護サービスを利用することが一般的です。
- ポイント:
低料金で利用しやすい。食事提供、生活相談、緊急時対応などのサービスがあります。 - こんな方におすすめ:
自立した生活を送れるが、見守りや生活支援があると安心な方。費用を抑えたい方。
介護が必要な高齢者向け:安心のサポートを受けられる住まい
日常生活に介護が必要になった高齢者の方には、介護サービスが充実した住まいを選ぶことが重要になります。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、食事、洗濯、掃除などの生活支援サービスに加え、入浴や排泄の介助、機能訓練など、介護保険を利用した介護サービスを施設内で受けることができる施設です。24時間体制で介護職員が常駐しており、手厚いケアが必要な方にとって安心できる住まいです。
- ポイント:
食事、掃除、洗濯などの生活支援サービスに加え、排泄や入浴、機能訓練など24時間体制で介護サービスを提供します。医療機関との連携体制が整っている施設が多いです。 - こんな方におすすめ:
日常生活に介護が必要、要介護認定を受けている方。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)は、重度の要介護者の方を対象とした公的な介護保険施設です。
生活介護を中心に、機能訓練や健康管理など、総合的なサービスを提供しています。
費用が比較的安価なため入所希望者が多く、待機期間が長い場合があります。
- ポイント:
要介護3~5と、重度の要介護者向けの公的施設です。費用が比較的安価です。 - こんな方におすすめ:
重度の介護が必要で、できるだけ費用を抑えたい方。
介護医療院・介護療養型医療施設
介護医療院と介護療養型医療施設は、長期的な医療ケアと介護が必要な高齢者のための施設です。
医療的なケアが中心でありながら、日常生活の支援やリハビリテーションも行われます。
- ポイント:
医療ケアと介護の両方を提供します。
長期的な療養が必要な方向けです。 - こんな方におすすめ:
慢性的な病気があり、医療的なケアと介護が必要な方。
グループホーム
グループホームは、認知症の高齢者の方が少人数で共同生活を送る住まいです。
家庭的な雰囲気の中で、専門のスタッフによるサポートを受けながら、自立、かつ穏やかな生活を送ることができます。
- ポイント:
認知症の高齢者向けの少人数制施設で、自立した生活を維持できるよう支援を受けられます。 - こんな方におすすめ:
認知症と診断された方で、自宅での生活は困難ながらも、集団生活に適応できる方。
住まいの種類を選ぶ際の重要なポイント
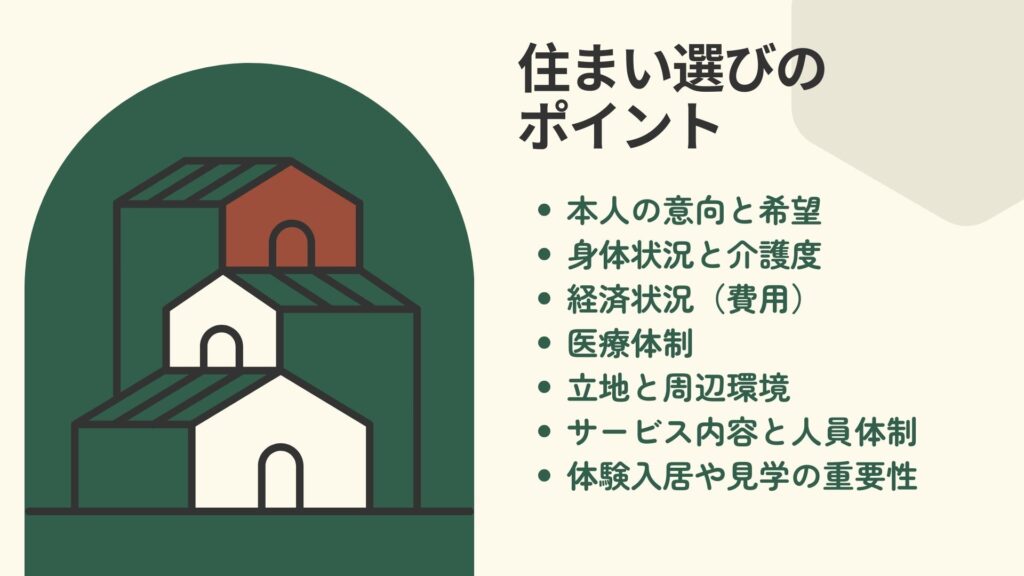
数多くの高齢者向け住まいの種類の中から、最適な住まいを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
本人の意向と希望
最も大切なのは、高齢者ご本人の「どのような場所で、どのように暮らしたいか」という意向を尊重することです。
住み慣れた地域で暮らしたい、活動的に趣味を楽しみたい、静かな環境で穏やかに過ごしたいなど、ご本人の希望を丁寧に聞き取りましょう。
しかし中には、認知症であったり、言葉が話せないなどのために、意向を確認できないこともあるかもしれません。
また、住まいへの転居にご本人が否定的だった場合、入居がスムーズにいかない可能性が高くなります。
その場合は、後述する相談窓口に問い合わせてみましょう。
すでに入居を検討する施設スタッフと連絡がとれる状況にあれば、スタッフに相談するのも良いかもしれません。
どの高齢者も、基本的には「自宅にいたい」という希望をお持ちの方がほとんどです。
住み慣れた自宅を離れるという不安は、簡単に拭い去れるものではなく、ご本人とご家族だけでは話が平行線になることもしばしば。
施設スタッフなどがその間に入ってくれると、話がスムーズに進むかもしれないので、相談は積極的にしていきましょう。
身体状況と介護度
現在の身体状況や介護の必要度合いによって、適切な住まいの種類は大きく異なります。
将来的な身体状況の変化も見据え、必要なサービスを受けられる住まいを選ぶことが重要です。
例えば、先述したように、概ね生活の支障がない方はサービス付き高齢者向け住宅やシニア向け分譲マンションなどが適しています。
グループホームは、認知症の診断を受けていることが入居要件の一つですが、認知症の人は必ずグループホームに入るべき…というわけではありません。
認知症であっても、軽度であったり、日常生活がある程度自立している、集団生活に支障がないといった状態であれば、住まいの選択肢を広げることができます。
また、介護保険の認定を受けている場合は、その介護度も参考にしましょう。
介護施設の多くは介護度を入居要件に取り入れているところが多いためです。
経済状況(費用)
高齢者向け住まいの費用は、施設の種類やサービス内容によって大きく異なります。
入居一時金、月額利用料、介護費用などを考慮し、無理のない範囲で継続して支払える住まいを選ぶことが大切です。
経済状況に応じた例:
- 生活は概ね自立していて、経済状況にも余裕がある
⇒サービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンション、住宅型有料老人ホーム - 生活は概ね自立しているが、費用は抑えたい
⇒ケアハウス - 要介護度が高く、費用は抑えたい
⇒特別養護老人ホーム
※上記はあくまで一例であり、その他の状況次第ではさらに選択肢が増える可能性があります。
また、収入に応じて、介護保険など公的な補助制度などが利用可能な場合もあるので、相談窓口や施設スタッフに問い合わせてみることをオススメします。
医療体制
持病や既往歴がある場合は、医療体制が整っている住まいを選ぶことが重要です。
施設によって、通院にご家族の付き添いが必要だったり、医師の往診があるため主治医が変更になるなどの場合があります。
協力医療機関の有無や、 定期的な診察、緊急時の対応などを確認しておきましょう。
立地と周辺環境
住み慣れた地域からの転居は、高齢者にとって大きな環境の変化となります。
実際に入居される方の中には、「せめて、遠くではなく地元の施設に入りたい」とご希望される方も少なくありません。
ご本人が安心できる環境を選ぶことも重要ですし、何かの時にご家族が通いやすい立地であることもポイントです。
サービス内容と人員体制
提供されるサービスの内容や、介護・看護職員の人数、介護福祉士の資格保有者などを確認しましょう。
人員体制が全てではありませんが、
ご本人のニーズに合ったサービスが提供されているか、十分な人員体制が整っているかは、安心して生活を送る上で非常に重要です。
体験入居や見学の重要性
候補となる住まいが見つかったら、必ず体験入居や見学を行いましょう。
実際に生活してみると、資料や説明だけではわからない部分が見え。施設の雰囲気やサービス、職員の対応などを肌で感じることができます。
可能であれば、複数の施設を見学し、比較検討することをおすすめします。
どこに相談すればいい?住まい探しの相談窓口
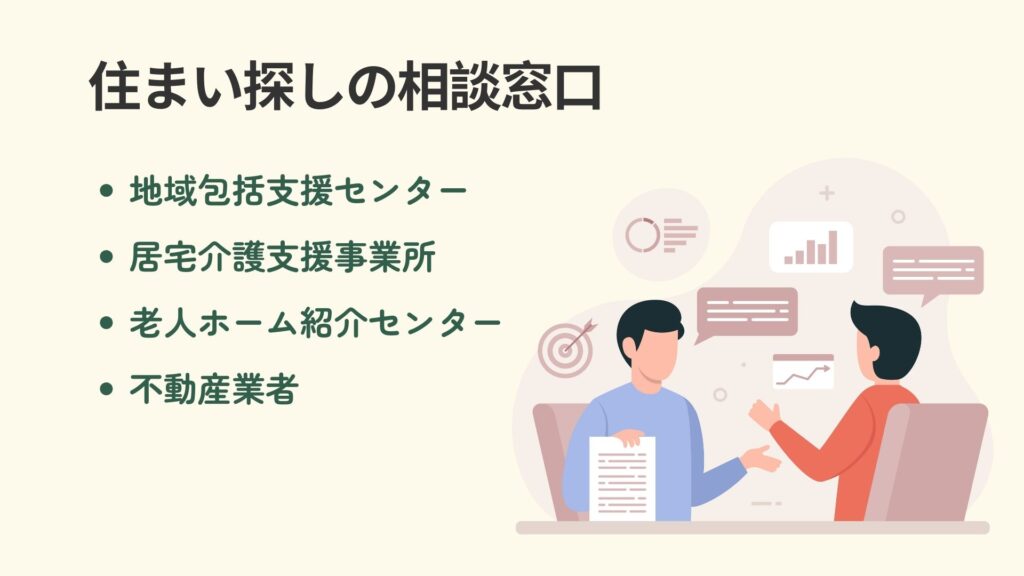
高齢者の住まい探しは、情報収集から見学、契約まで、いくつかの手順を踏む必要があります。
困ったときや迷ったときは、以下の相談窓口を積極的に活用しましょう。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支援する地域の拠点です。
介護保険サービスに関する相談はもちろん、住まいに関する情報提供や相談も行っています。
お住まいの地域の地域包括支援センターに、まずは相談してみることをおすすめします。
ただし、基本的に地域包括支援センターで行えるのは、施設の紹介までです。
問い合わせや申し込みなどは、ご本人かご家族で行う必要があります。
居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所には、ケアマネジャー(介護支援専門員)が在籍しており、介護保険サービスの利用に関する相談や、ケアプランの作成などを行っています。
在宅での生活を続けながら、将来的に住み替えを検討している場合などにも相談できます。
もちろん、最初から施設の紹介を依頼することもできますが、地域包括支援センター同様、できるのは基本的に紹介までです。
老人ホーム紹介センター
民間の老人ホーム紹介センターは、様々な種類の高齢者向け住まいの情報を提供し、入居相談や見学の手配などを行っています。
インターネットや電話で気軽に相談できるところが多いです。
最近ではこうした事業を民間で行うところも増えてきました。
中には、身寄りのない方のために、身元保証人になってくれる事業もあるので、よく話を聞いてみるといいでしょう。
このような事業の情報は、地域包括支援センターやケアマネジャーの他、意外にも病院から得られる場合もあります。
入院中から施設を検討する場合は、病院に相談するのも良いかもしれません。
不動産業者
高齢者向け住宅に特化した不動産業者も存在します。
賃貸物件だけでなく、シニア向け分譲マンションなどの情報も扱っているので、専門的な知識を有している可能性もあるでしょう。
住まい選びに失敗しないために
高齢者の住まい選びで後悔しないためには、事前の情報収集と慎重な検討が不可欠です。
ここでは、失敗しない住まい選びに重要なポイントを確認していきましょう。
- 費用の相場は?:
高齢者向け住まいの費用は、種類や地域、サービス内容によって大きく異なります。
事前にインターネットや相談窓口で情報収集を行い、予算感を把握しておきましょう。
ポイントは、かい複数の施設を比較検討することが大切です。 - 入居までの流れ:
資料請求、見学、体験入居、契約といった一般的な流れがあります。
施設によっては、 事前面談や健康診断などが必要な場合もあります。事前にしっかりと確認しておきましょう。 - それぞれの施設の違いは?:
この記事で解説したように、高齢者向けの住まいの種類は様々です。
それぞれの特徴やサービス内容、費用などをしっかりと理解し、ご本人の状態やニーズに合った施設を選ぶことが重要です。 - 後悔しない選び方:
ご本人の意向を尊重し、身体状況や経済状況、将来の見通しなどを総合的に考慮して選びましょう。
インターネットの情報だけでなく、実際に施設を見学し、職員の方と話したり、体験入居をしたりすることをおすすめします。 - 体験入居の注意点:
体験入居は、施設の雰囲気を実際に体験できる貴重な機会です。
食事の内容、居室の環境、職員の対応などを 注意深く観察しましょう。疑問点や不安な点は、遠慮せずに質問することが大切です。
まとめ
高齢者の住まいの種類は多岐にわたり、ご本人の状態や希望、経済状況によって最適な選択肢は異なります。
この記事では、それぞれの住まいの特徴や選び方のポイント、相談窓口について解説しました。
後悔しない住まい選びのためには、ご本人の意向を尊重し、身体状況や費用、将来の見通しを考慮した上で、情報収集や見学、体験入居を通じて慎重に検討することが重要です。
迷った際は、地域包括支援センターなどの専門機関に相談し、最適な住まいを見つけましょう。
- 高齢者の住まいは「元気な方向け」と「介護が必要な方向け」に大別される
- 元気な方向け: 自由度が高く、生活支援を受けられる「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」や、資産にもなる「シニア向け分譲マンション」などがある。
- 介護が必要な方向け: 24時間体制の介護が受けられる「介護付き有料老人ホーム」や、費用を抑えやすい公的施設「特別養護老人ホーム(特養)」、認知症ケアに特化した「グループホーム」などがある。
- 最適な住まいを選ぶための5つの重要ポイント
- 本人の意向:「どんな暮らしがしたいか」を尊重することが最も大切。
- 身体状況と介護度: 現在と将来の状態を見据えて、必要なサービスを受けられるか確認する。
- 経済状況(費用): 無理なく支払い続けられるか、入居一時金と月額費用を把握する。
- 医療体制: 持病がある場合は、協力医療機関や緊急時の対応を確認することが不可欠。
- 立地と環境: 本人が安心でき、家族が通いやすい場所を選ぶ。
- 候補が決まったら「見学・体験入居」は必須
- 資料だけでは分からない施設の雰囲気、スタッフの対応、食事の内容などを肌で感じることが、後悔しないための鍵。
- 迷ったら一人で抱え込まず「専門家」に相談する
- 「地域包括支援センター」や「ケアマネジャー」、「老人ホーム紹介センター」など、無料で相談できる窓口を積極的に活用する。
高齢者の住まい選び【Q&A】
高齢者の住まい選びに関して、多くの方が抱く疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1. 介護はまだ必要ないのですが、将来に備えたいです。どんな住まいがおすすめですか?
A1. まだお元気で活動的な方には、自立した生活を送りながら万が一の時に備えられる住まいがおすすめです。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住): 安否確認や生活相談サービスが付いたバリアフリーの賃貸住宅で、自由な生活を送りたい方に適しています。
- シニア向け分譲マンション: 自分の資産として所有でき、レストランやフィットネスジムなどの共用施設が充実していることが多いです。
- 住宅型有料老人ホーム: 食事や掃除などの家事サポートを受けられ、自分の時間を趣味や交流に使いたい方に向いています。
これらの施設は、将来介護が必要になった際に、外部の介護サービスを利用しながら住み続けられる場合が多いです。
Q2. 日常的に介護が必要な家族の住まいを探しています。どんな選択肢がありますか?
A2. 日常的な介護や医療的ケアが必要な方には、24時間体制でサポートを受けられる施設が安心です。
- 介護付き有料老人ホーム: 介護スタッフが24時間常駐し、食事や入浴、排泄の介助からリハビリまで、施設内で手厚い介護サービスを受けられます。
- 特別養護老人ホーム(特養): 原則として要介護3以上の方が入居できる公的な施設です。費用が比較的安価なため、入居待機者が多い傾向にあります。
- グループホーム: 認知症の診断を受けた方が、少人数で家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る施設です。専門スタッフの支援を受けながら、穏やかに過ごせます。
ご本人の要介護度や必要なケアの内容によって最適な施設は異なります。
Q3. 「有料老人ホーム」と「特養」「サ高住」の違いがよく分かりません。
A3. 主に「運営主体」と「提供されるサービス」に違いがあります。
- 有料老人ホーム: 民間企業が運営。生活支援中心の「住宅型」と、介護サービスまで提供する「介護付き」があります。サービスが手厚い分、費用は高めになる傾向があります。
- 特別養護老人ホーム(特養): 地方公共団体や社会福祉法人が運営する「公的施設」です。手厚い介護を比較的低い費用で受けられますが、入居要件が厳しく待機期間が長いことがあります。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住): 民間企業などが運営する「賃貸住宅」です。安否確認と生活相談が基本サービスで、介護サービスは外部事業者と個別に契約するのが一般的です。
Q4. 施設選びで後悔しないために、一番大切なことは何ですか?
A4. 最も大切なのは**「ご本人の意向を尊重し、ご本人が納得して決めること」**です。
ご家族が良かれと思って決めても、ご本人が納得していないと、新しい環境に馴染めず、生活の質が低下してしまうことがあります。ご本人の「こんな風に暮らしたい」という希望を丁寧にヒアリングしましょう。 もし、ご本人の意思確認が難しい場合や、話し合いが平行線になってしまう場合は、後述する「地域包括支援センター」やケアマネジャーといった第三者の専門家に間に入ってもらうのも有効な手段です。
Q5. 費用が心配です。どのくらい準備すればよいですか?
A5. 費用は施設の種類、地域、サービス内容によって大きく異なります。一般的に、入居時に支払う**「入居一時金」と、毎月支払う「月額利用料」**が必要です。
- 費用の目安(一例):
- 公的施設(特養・ケアハウスなど): 入居一時金は不要な場合が多く、月額利用料も所得に応じた負担軽減があるため、比較的安価です(例:月額10万円~15万円程度)。
- 民間施設(有料老人ホームなど): 入居一時金は0円~数千万円、月額利用料は15万円~数十万円と幅広いです。
まずは複数の施設の資料を取り寄せ、費用の内訳(家賃、管理費、食費、介護サービス費など)をしっかり確認しましょう。費用を抑えたい場合は、特養やケアハウスを検討したり、入居一時金が0円のプランを探したりする方法があります。
Q6. どこに相談に行けば、客観的なアドバイスをもらえますか?
A6. 住まい探しに迷ったら、以下の公的な相談窓口や専門家を活用することをおすすめします。
- 地域包括支援センター: 市区町村が設置する、高齢者のための総合相談窓口です。お住まいの地域の施設情報や介護保険について、無料で相談できます。まずはここから始めるのが良いでしょう。
- ケアマネジャー(居宅介護支援事業所): すでに要介護認定を受けている場合は、担当のケアマネジャーが最適な住まい選びの相談に乗ってくれます。
- 老人ホーム紹介センター: 民間の紹介センターも、様々な施設の情報を持っており、見学の予約代行などを行ってくれる場合があります。相談は無料のところが多いです。
これらの窓口は、ご本人やご家族の状況を客観的に判断し、適切な選択肢を提案してくれます。一人で抱え込まず、積極的に相談しましょう。
認知症にお悩みの方へ
もしあなたが、またはあなたの大切な方が認知症のことで悩んでいらっしゃるなら、私たちがお力になれるかもしれません。
▼公式LINEで無料相談を受け付けています
「もしかして認知症かも…」「将来が不安…」どんな些細なことでも構いません。
その不安に寄り添い、認知症治療をサポートします。今すぐLINE登録して、安心への扉を開きませんか?
▼LINE登録者限定!自宅でできる認知症改善メソッドを無料プレゼント
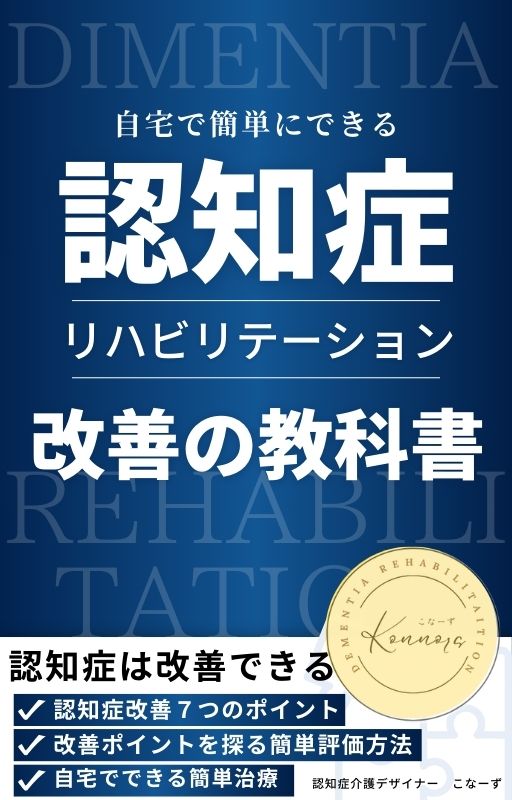
LINEにご登録いただいた方には、自宅で取り組める認知症改善メソッドが満載の「認知症改善の教科書」を無料でプレゼントしています。
薬だけに頼らない、 新しいアプローチで、穏やかな生活を取り戻しましょう。
ぜひ、 この機会にご登録ください。
⇓⇓⇓