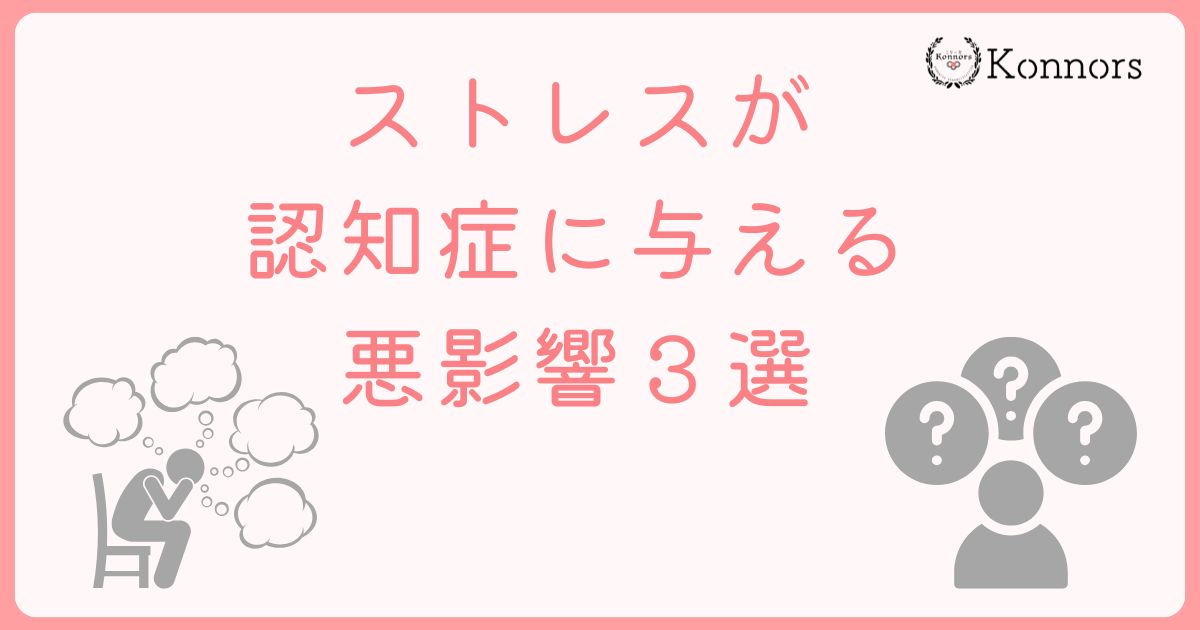はじめに:なぜストレスが認知症に影響を与えるのか?

ストレスと認知症の関係性
皆さんは、ストレスが認知症に与える影響についてご存じでしょうか?
私は長年、介護士や認知症リハビリテーション専門士として、多くの認知症患者さんと向き合ってきました。
その経験から、ストレスが認知症の発症や進行に深く関わっていることを実感しています。
あるご家庭では、認知症の母親を介護されていた娘さんがいらっしゃいました。
母親の介護は、娘さんに多大な精神的な負担をかけており、夜も眠れない日が続いたり、イライラしやすくなったりと、ストレスが顕著に見られました。
その結果、娘さん自身の記憶力や集中力が低下し、日常生活にも支障が出てきたというケースがありました。
ストレスが原因で、介護をしていた家族までもが、介護が必要になった事例です。
ストレスが脳に与える影響について、最新の研究データに基づいた解説
ストレスを感じると、私たちの体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。
このコルチゾールは、短期的には体を活性化させる働きがありますが、長期的に過剰に分泌されると、脳の神経細胞を傷つけ、特に記憶を司る海馬を萎縮させてしまうことが、最近の研究で明らかになっています。
また、過剰なストレスは認知症だけでなく、うつ病や生活習慣病など、様々な心身の不調を招きます。
認知症の介護をしているご家庭では、少なからず、本人・介護者両方にストレスがありますので、そのままにしていては、状況を悪化させる一方になるでしょう。
認知症の種類とストレスとの関連性(アルツハイマー型、脳血管性など)
ストレスが認知症のリスクを高めることは、先ほどお話しした通りです。
主に、アルツハイマー型認知症のケースが多いと思われます。
しかし実際には、アルツハイマー型認知症だけでなく、脳血管性認知症の発症リスクも高めます。
高血圧や動脈硬化といった生活習慣病は、ストレスによって悪化しやすく、脳梗塞や脳出血を引き起こす可能性が高まります。
また、ストレスは免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなることで、間接的に認知症の発症リスクを高めることもあります。
広い意味で言えば、便秘はアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の原因であるという仮説が有力視されつつありますが、便秘もまた、ストレスが原因で起こる場合があるのです。
ストレスが認知症に与える3つの具体的な悪影響
ここまでお話ししたことを、簡単に3つの具体例にまとめます。
脳の萎縮を加速させる
ストレスによって分泌されるコルチゾールは、海馬の神経細胞を死滅させ、脳の萎縮を加速させます。
海馬は記憶を司る重要な部位であり、その萎縮は記憶力の低下や見当識障害といった認知症の症状を招きます。
実際に、私が関わった患者さんの中には、40代から始まった父親の介護ストレスが原因で、50代半ばからご自身の記憶力が低下し、パートの仕事でミスが増えたり、友人と待ち合わせなどの約束を忘れてしまうことが増えていったという方がいらっしゃいました。
その方は、60歳になる頃に検査を受け、軽度ながら脳委縮が認められ、初期のアルツハイマー型認知症と診断を受けています。
萎縮とは別ですが、ストレスによる脳への影響として、うつ病などの精神症状を合併することもあります。
脳血管障害のリスクを高める
ストレスは、交感神経を過剰に刺激し、血圧を上昇させます。
高血圧は、動脈硬化を促進し、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害のリスクを高めます。
また、ストレスは心身症を引き起こしやすく、頭痛や不眠、めまいといった症状を悪化させ、脳血管障害の発症に繋がることがあります。
実際に、ストレスが原因で脳梗塞を発症し、半身麻痺が残ってしまった方も少なくありません。
免疫機能を低下させる
ストレスは、免疫細胞の働きを抑制し、免疫力を低下させます。
免疫力が低下すると、感染症にかかりやすくなり、肺炎や尿路感染症などの合併症を引き起こすリスクが高まります。
これらの合併症は、認知症の症状を悪化させ、予後を悪くする可能性があります。
事実として、認知症患者の多くは、肺や腸が機能低下している場合が多いのです。
認知症のせいでそうなったという見方もありますが、仮にそうだとしても、内臓の機能低下は、それだけで認知機能を低下させるため、悪化の悪循環に陥っているとも見られます。
ストレスを軽減し、認知症予防・改善に繋げる方法

ストレスチェックとセルフケア
ストレスは自覚がない場合もあります。
定期的にストレスチェックを行うことで、今自分がどのような状態にあるか知っておくことは重要です。
社団法人 全国老人保健施設協会では、以下のようなストレスチェックシートを公開しています。
✅介護やお世話のために、身体の具合が悪くなったことはありますか
✅介護やお世話は、つらいと思いますか
✅介護やお世話のため、自由に外出できないことはありますか
✅介護やお世話のため、睡眠不足になっていますか
✅介護やお世話のため、家事や仕事に影響が出ていますか
✅介護やお世話のための出費が、経済的な負担となっていますか
✅もう少し自分の時間がほしいと思いますか
✅介護やお世話に対して、もう少しほかの家族が理解してくれればいいと思いますか
✅介護やお世話をするようになってから、家族関係が気まずくなったと思いますか
✅介護やお世話のことで、相談できる専門家はいますか
✅介護やお世話を変わってくれる人はいますか
✅介護やお世話に関することで、グチを言い合える人はいますか
✅あなたの介護やお世話に対して。ご本には感謝していると思いますか
✅これからも今までのような介護やお世話をしていこうと思いますか
引用:社団法人 全国老人保健施設協会
他にもいろんなサイトで、介護者向けのストレスチェックを公表しています。
合う合わないもあると思うので、いくつか試してみてもいいでしょう。
もし、ストレスチェックで該当項目が多かったり、ストレスを自覚していた場合は、まずは深呼吸をしてリラックスしたり、自然の中に出てみたりするなど、簡単なセルフケアを試してみましょう。
生活習慣の見直し
規則正しい生活を送ることは、ストレスを軽減し、認知機能を維持するために非常に重要です。
十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動をすることで、心身のリラックス効果が得られます。
自分に合った趣味や活動を見つけることも、ストレス解消に役立ちます。
また、飲酒や喫煙も生活習慣の一種です。
お酒(特にビール)は利尿作用がコーヒーなどのカフェイン飲料とは段違いに強く、脱水状態を引き起こしやすくなります。
慢性的な脱水が続くと血液がドロドロになり、脳に血液が巡りにくく、認知症や動脈硬化のリスクも高まります。
タバコは、肺がんや動脈硬化のリスクを高めることはご存知でしょうか。
他にも、タバコに含まれる化学物質が脳の神経細胞にダメージを与えることで、認知症を引き起こしやすくなると言われています。
飲酒・喫煙を一気に断つのは、かえってストレスになるとお考えの方もいるかもしれません。
ですが、それを考慮しても、飲酒・喫煙を断つメリットの方が大きいと言えます。
少しずつでも良いので、お酒の量、タバコの本数を減らしてみてはいかがでしょうか。
心のケア
まずは、悩みを一人で抱え込まず、公共機関や信頼できる人に相談したり、カウンセリングを受けることも大切です。
瞑想やヨガなども、リラックス効果とその健康効果で、近年注目されています。
また、森林浴や温泉もおすすめです。
森の香り成分には免疫機能を高める効果があり、温泉成分には自律神経を整えるなど、健康上有効であると言われています。
自律神経を整えるという点では、お灸などを使った温熱療法も効果的です。
中でも特におすすめしたいのは、アロマテラピーです。
様々な香りがあり、それぞれいろんな効果があります。
ラベンダーの香りなどはリラックス効果が高いことで知られていますが、柑橘系の香りは、脳(特に海馬)を活性化させると言われており、介護業界でも多く取り入れられています。
環境の改善
ストレスの原因となる環境を見直すことも大切です。
人間関係がストレスの原因になっている場合は、信頼できる人に相談したり、関係性を改善するための努力をしたりしましょう。
はっきり言ってしまえば、自分がつらい時に、心無い発言をするような人がいる場合は、聞き流すか、すっぱりと関係を絶つことをおすすめします。
また、仕事や家事など、負担に感じていることを整理し、優先順位をつけることも効果的です。
栄養バランスの改善
バランスの取れた食事は、心身のリラックスを促し、ストレスに打ち勝つ力を与えてくれます。
特に、ビタミンB群やマグネシウムは、ストレス軽減に効果があるとされています。
そういうことを意識することも気持ち的に難しい場合は、たまにはいっそ何も気にせず、おいしいものを食べて気分転換を図ることもいいかもしれません。
また、ストレス発散にお酒を飲まれる方も少なくないかと思います。
確かに、楽しいお酒の席でストレスが解消されることもありますが、日常的な、あるいは過剰なアルコール摂取は、それ自体が認知症や多数の病気の元になりますので、どうしても飲みたいという場合は、たまのお楽しみ程度にとどめておきましょう。
睡眠の質の向上
質の高い睡眠は、認知症の改善に効果があるとの研究結果があります。
寝る前のスマホの使用を控えたり、リラックスできる環境を整えたりすることで、睡眠の質を向上させることができます。
他にも、枕を自分に合ったものや天然素材のものに変えてみたり、寝る2時間前に照明を暖色系や間接照明に変えることも効果的です。
また、トイレが近くなるという理由で毛嫌いされがちですが、寝る前にコップ一杯の白湯を飲むと睡眠の質が高まると言われています。
睡眠時無呼吸症候群があると睡眠の質が下がってしまうので、夜寝ている時の呼吸状態を確認し、数十秒以上呼吸が止まっていることがある場合は、医師への相談をおすすめします。
定期的な運動
運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールによる悪影響を抑制し、幸福ホルモンであるセロトニンの分泌を促進します。
自分に合った運動を継続することで、心身のリラックス効果が得られます。
運動が苦手な方でも、まずは数百メートルから意識的に歩いてみると、寝つきが良くなるなどの効果があるかもしれません。
歩く時のコツは、全身の筋肉の動きと、少しだけ心拍数が上がるような速さを意識することです。
もちろん、動画などを見ながら宅トレをするのでも構いません。
歩いたり、長時間経っているのが難しい方の場合は、座ったままできる運動もたくさんあるので、無理ない範囲で挑戦していくと良いでしょう。
「とにかく歩かせよう!」のような自己判断は危険を伴うので、医師や理学療法士など、専門家に相談することが重要です。
まとめ:ストレスと上手に付き合い、認知症を改善するために
ここまで、ストレスが認知症に与える悪影響と、その具体的なメカニズムについて解説してきました。
ストレスは必ずしも悪いものだけではなく、私たちの生活に不可欠なものです。
どちらにせよ、ストレスを完全に避けることは難しいかもしれません。
しかし、ストレスと上手に付き合うことで、認知症のリスクを低減し、より健康的な生活を送ることができます。
ストレスは、認知症の発症や進行に深く関わっていますが、適切な対処法を実践することで、その影響を軽減することができます。
この記事で紹介した方法を参考に、ご自身の生活に取り入れてみてください。
認知症について悩んでいる方は、公式LINEで無料相談をお受けしておりますので、お気軽に相談してください。
【コナーズ公式LINE】

【参考文献】
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
- 国立長寿医療研究センター:https://www.ncgg.go.jp/